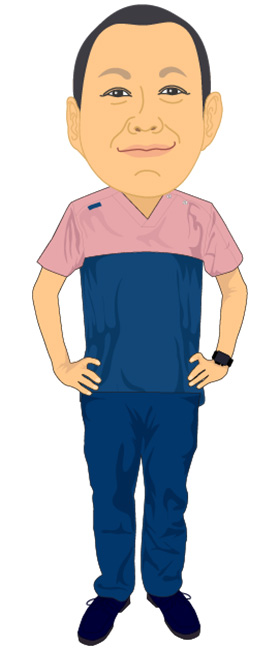重要なのは「予測」と「準備」
病院薬剤師として活動をスタート
看護師だった母の勧めもあり、病院薬剤師という道を選んだ二十軒栄亮さん。病院では、患者の服薬指導や持参薬の管理など、病棟業務を行う一方、救急医療やクリニカルパス管理、化学療法、緩和ケアなどさまざまなチーム医療に携わってきたといいます。
「化学療法に関する業務を多く行っていたことから、自然と緩和ケアに携わるようになり、さまざまな薬学的アプローチを行ってきました。緩和ケアの対象者はがんの患者さんのみならず、さまざまな疾患の終末期、特に症状の強い方の対応が多かったと思います。病院のほうが安心できるという患者さんもいらっしゃいますが、やはり『自宅に帰りたい』とおっしゃる方は大勢います。ただ、その当時は在宅で使用できる麻薬も限られており、また『麻薬を使用する』ということに医療者自身が慣れていないことも多く、何より在宅緩和医療に対応できる薬局がありませんでした。こうした現実に課題意識を感じており、地域の医療関係者の方々とさまざまな角度から話し合いや情報共有を行ってきましたが、状況は大きくは変わりませんでした。そこで、知人の勧めもあり『それなら自分でやってみよう』と思ったのが、薬局立ち上げの大きなきっかけです」と話す二十軒さん。

2019年に大和郡山市でさなえ薬局を開局。その後、在宅医療のニーズ増加に伴い、天理市に2店舗目を開局しました。
二十軒さんは、自身が病院薬剤師として活動していたエリアとは全く異なる場所で開局したため、文字通りゼロからのスタートだったそうです。
「頼れる人もいなかったので、とにかく地道に営業し続けました。知り合った医師にまた別の医師を紹介いただくなどひたすら営業活動と信頼獲得のための実績づくりを行う毎日で、それは本当に大変でした」と話します。その活動が功を奏し、現在では約80名の患者さんに対し、月に250件ほどの訪問を実施しているそうです。
意識しているのは「単なる薬の配達屋にならないこと」で、患者としっかりとしたコミュニケーションを取り、普段と違うところがないか注意深く観察することを重視しているといいます。
「病院では、カルテを見れば患者さんの情報が分かりますが、在宅医療ではそれは容易ではありません。そのため、自ら動き、積極的に患者さんの情報を取りにいく姿勢がとても重要になります。そうしていれば、今後起こりうる状況変化の『予測』ができ『準備』ができます。常日頃から十分なモニタリングを行っていれば、さまざまな変化にもしっかりと対応できると考えています」と二十軒先生は話してくれました。
医師や看護師から寄せられる絶大な信頼
病院と薬局では「薬剤師の役割自体が大きく異なる」と話すのは、西川実希子さん。例えば点滴治療を行う際、病院では必要な物品は看護師が準備しますが、在宅では薬局が担当するため、多角的な知識が必要になるといいます。また、病棟では看護師が日に何度か点滴を交換することができますが、在宅では簡単ではありません。
加えて、採血やそれに対する医療者の評価頻度も、入院患者さんと比べると少ない環境であるため、短期経過を予測しながら実際の変化値との補正を行うことが重要です。そのためさなえ薬局では、患者さんの血液データを確認し、それぞれの患者さんの現状にあった処方設計も行っています。病院と在宅では、視点を変える必要があるそうです。
「訪問回数を増やすことは不可能ではありませんが、それでは患者さんの経済的負担が増え、また薬剤師のマンパワーも不足します。そのため少ない訪問回数でもパフォーマンスを上げる努力をしています。もちろん、患者さんの希望が最優先ですが、医師の希望も聞き、患者さんに携わる全員の希望にできるだけ添えるよう調整しています」と西川さん。
これまで西川さんが携わってきた患者さんの中で、最も心に残っているのは、在宅医療が始まったとき、痛みと嘔吐がひどく「死にたい」というほど苦しんでいた患者さんです。さなえ薬局が在宅医療にかかわることになり、持続的な皮下注射を行ったことで痛み・吐き気がなくなり、食事を摂ることもできました。「最期の時間を穏やかに過ごしてもらえたことは、今でも心に残っています」といいます。

またさなえ薬局では、コンパクトな精密持続注入ポンプを用いた処方提案も行っており、医師や看護師に対し、投与量や速度の設定など、機器の使い方までレクチャーしています。そのホスピタリティの高さは医師の間でも話題となり、連携先の医療機関より初めて紹介された医師からは「(さなえ薬局と連携すると)すべてお任せできて安心だよ」と言われ、頼りにされていると実感するそうです。
職域を狭めるのも広げるのも自分自身
多くの医療者に頼られる褥瘡のプロフェッショナル
さなえ薬局には全国で約30人という褥瘡・創傷専門薬剤師の1人が常駐しています。長年緩和ケアに携わり、褥瘡教育セミナーへの参加をきっかけに学び始めたという長谷川雅子さんは、薬剤を効果的に使い、褥瘡の治療期間を大幅に短縮することができる療法を習得、2024年に専門薬剤師となったそうです。

「医学部では褥瘡について専門的に学ぶ時間が多くはないため、褥瘡の薬剤について詳しくない医師もいます。ですから、褥瘡分野における薬剤師は、医師や看護師から頼られることも多いのです」と話す長谷川さん。実は、救急で運び込まれる高齢患者の多くに褥瘡が見られるものの、メインの疾患に対する治療が最優先となり、褥瘡治療が後回しになってしまうことが多いといいます。この実態に課題感を持っていた長谷川さんは、病院薬剤師時代に独自のプロトコルを開発。そのプロトコルとは、「褥瘡のある新規患者が入院した際、すぐに薬剤師に連絡。薬剤師は医師へ薬剤処方提案を行い、それを受けた看護師が褥瘡ケアを行う」というもの。これにより、褥瘡治療の遅れがなくなったといいます。
「病院でも在宅医療でも、褥瘡治療で最も重要なことはアセスメントです。特に在宅医療では、発生した原因を取り除くためのマットレスの選択や体圧を分散させるポジショニングなど、薬剤以外への幅広い知識が必要となります」と話す長谷川さん。
また専門薬剤師のみならず、褥瘡・創傷の認定薬剤師も全国で600人程度です。つまり「これから褥瘡を学ぶことで薬剤師の活躍の場は広がると思います」と長谷川さんはいいます。
これは、「自らの職域を制限し業務の幅を狭めてしまうのは薬剤師自身の問題であり、貪欲に挑戦し業務の幅を広げられるのもまた薬剤師自身」という二十軒さんの考え方とも通じており、これからの薬剤師に向けた期待や可能性を感じる言葉でした。
病院同様の医療を提供する「在宅」という醍醐味
「今でも忘れられないエピソードがあるんです」と話してくれたのは、天理さなえ薬局の管理薬剤師・岡本圭史さん。
「その方は、いわゆる医療資源が少ない地域にお住まいの末期がんの患者さん。終末期を自宅で迎えたいというご希望をかなえるため、オピオイドの投与や麻薬の持続皮下注射を組み合わせ対応しました。住み慣れた場所で最期まで穏やかに過ごしていただけたことは、患者さんやご家族の思いに寄り添えた大切な経験となっています。そして、大きな医療機関がない場所でも、病院同様の環境下で医療を受けることができる在宅医療の重要性を、改めて感じさせられました」と話してくれました。

一方で、さまざまな制約がある中、緊急対応を求められることが多い在宅医療において、薬剤師の役割が医療関係者に対し十分に認知されていないことは大きな課題、と岡本さんはいいます。
「私たちが連携する医師や看護師の方々からは、薬剤師の介入により薬剤管理がスムーズになったという評価をいただいており、大きな自信につながっています。薬剤師の専門性はさまざまな現場で発揮されており、その重要性を広く知ってもらう活動もまた必要だと感じています」と話します。
医療資源が少ない地域への対応については、二十軒さんも企業として大事にしていることであるといい、「どこに住んでいても病院と同じ質の医療を提供したい、その中で薬剤師としてできることを実践したい」という理念を掲げています。
医療者も患者も「人」
「圧倒的な経験値」がなせるサポート力
在宅医療におけるさまざまな専門性を備えるプロフェッショナル集団・さなえ薬局の最大の強みは「圧倒的な経験値である」と話す二十軒さん。その蓄積された経験は「おせっかいを進んで行うこと」から得られたものだといいます。
「私たちは、薬剤師である前に医療者、そして医療者である前に人。同じように、患者さんも人です。つまり、人と人として向き合うことを意識し、その関わり合いの中で必要なおせっかいは進んで行うことを理念としています。例えば夜間や休日など、どんなタイミングでも駆け付け、急な状況変化にも対応することで感謝の言葉をいただくこともありますが、すべては『予測』と『準備』によるもの。つまり、突発的な状況変化は、日々のモニタリングによって予測できる結果であり、それに向けて常に私たちは準備しているのです。だからこそ、私たちが行うモニタリングはとても重要なものだと考えています」と二十軒さんは、力強く語ってくれました。

緩和ケアの根本を考え、心血を注ぐ二十軒さんらしいエピソードであり、これもまたさなえ薬局の魅力のひとつなのでしょう。
さなえ薬局の「おせっかい」は、今日も続いています。
編集:株式会社 医学アカデミー