漢方薬を扱う薬剤師として広島で開業
涙あふれた思い出のエピソード
桃原さんが薬剤師を目指したきっかけには、伯祖父であり、宮古島出身者として初の医学博士でもあった砂川正亮氏の存在があったそうです。
「当時も今もそうですが、沖縄県内には薬学部がないため福岡の大学に進学しました。その頃は飛行機代も高額だったので簡単に家には帰れませんから、まるで今生の別れのような気持ちで出発しました。福岡に着いてからしばらくの間は、まさに『涙そうそう』(涙がぽろぽろあふれる様子)でしたね」と話す桃原さん。大学卒業後は、生薬学の教授であった恩師の勧めにより、広島にいた先輩のもとで生薬を学びながら薬剤師として働き始めました。白衣が真っ黒になるほど、一日中薬草と向き合っていたといいます。
この経験を経て、29歳で保険薬局をスタート。若いうちにさまざまな経験を積もうと、あえて沖縄には戻らず広島での開局を選択したそうです。薬局内に漢方コーナーをつくり、さまざまな相談を受けながら地道に努力してきたと話す桃原さんですが、その中で忘れられないエピソードがあると言います。
「漢方薬が欲しいと、あるご夫婦が来局されました。お話を聞くと、結婚されてから何年も不妊に悩まれていたそうです。その後、1年近く頑張って通ってくださり、ついにご妊娠。出産後すぐに赤ちゃんを連れて来てくれたのですが、よくここまで頑張ったなという思いがあふれ、まるで我が子のことのようにうれしくて涙が止まりませんでした」。
漢方薬の処方は、その人の体調や悩み、気持ちに寄り添いながら薬を選び、一人ひとりに合ったものを処方するという繊細な仕事。丁寧なコミュニケーションと高い専門知識が必要とされますが、桃原さんは熱心に、そして真摯に患者さんと向き合ってきたそうです。
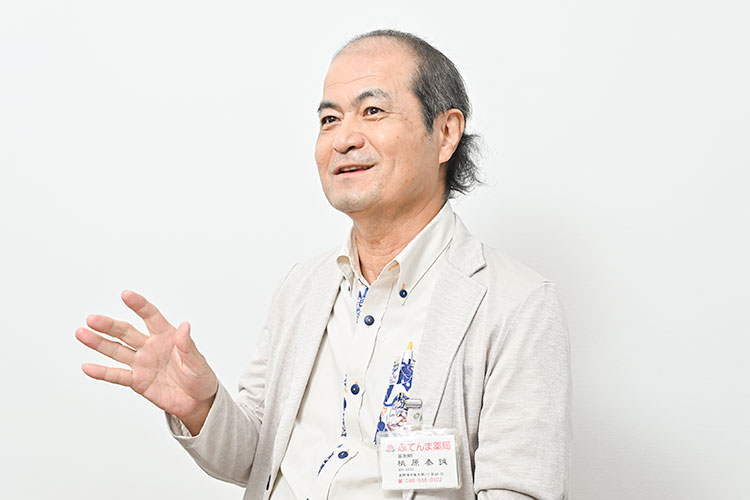
「学校薬剤師」は薬剤師としての大きな使命
子どもたちに正しい知識を届けたい
今から約20年前、桃原さんは広島での経験を糧に、ついに沖縄本島でも薬局をスタートさせます。当時の心境を「まさに故郷に錦を飾る、という気持ち」と話す桃原さん。現在は学校薬剤師としても活動され、水質や温度、照度検査のほかに、騒音測定なども行っています。
「ここ普天間では、昼夜を問わず航空機の音が聞こえます。市民生活をはじめ、子どもたちの学校生活にも大きな影響があることから、騒音測定は重要な仕事なのです」。
また、沖縄、広島ともに小中学校を中心に出張授業を実施。「薬物乱用防止教室」として講演を行い、薬物の種類や使用による弊害について説明し、勧められたときの断り方の練習など、ロールプレイングも交えながら教えています。特に沖縄は薬物関連の事件が多く、低年齢化も大きな問題となっています。中には、中身を知らないまま子どもたちがデリバリーを頼まれるなど、小遣い欲しさに巻き込まれてしまうケースも増えていると言います。全国的に広がる市販薬の過剰摂取の問題も含め、「子どもたちには正しい知識をもってほしい。こうした教育も、薬剤師としての重要な使命だと思っています」と桃原さんは話します。

「どこまでも患者さんに寄り添う」が桃原スタイル
長い経験からつかんだ患者さんとのコミュニケーション方法
「患者さんに薬をお渡しすることを『投薬』と書きますが決して投げ渡すわけではなく、またそういう気持ちで患者さんと向き合うことはありません。患者さんの目線にあわせて話を聞く。その中に共感があり、傾聴する部分があり、そこから患者さんの気持ちを汲み取る努力をします。病気の話を聞いてほしい患者さんもいれば、外来で長く待たされたので早く帰りたいと思っている患者さんもいます。薬の正しい使い方を説明する必要はありますが、相手に応じてどんな対応をすればよいかを考えながらコミュニケーションを取っていける薬剤師が増えてほしいと思います」と桃原さん。
患者さんによって声のかけ方を変えたり、本来椅子に座って説明するところを立ち話に変えたりと、桃原さんの患者さんへの対応は実にさまざま。
「顔や雰囲気を見ていると自然に分かってくる。これは、漢方薬の相談を長く行っていた経験が役に立っていると思います」と桃原さんは話します。

配達サービスの延長線上にある地域とのつながり
現在、広島に2店舗、沖縄に4店舗の薬局を運営している桃原さんは、近年新たな取り組みをスタートさせています。
契機となったのは、コロナ禍に患者さんに薬を届け始めたこと。感染が収束してからも、必要とする患者さんには配達サービスを続けていると言います。
「当薬局を利用してくれる患者さんには、ご年配の方が多く近隣の方がほとんどですが、腰や膝が痛い中、わざわざバスやタクシーを使って来局される方もいます。家族に頼みづらいから自分で歩いてきた、という方も。そういう方々にはできるだけ配達してあげたいと思っています。届けたときは玄関先でお渡しして終わることもあれば、室内にお邪魔して日常会話をすることもあります。話しているうちに残薬や飲み間違いに気づくことがあり、結果的にポリファーマシー対策にもなっているのです。年間に大量の薬が廃棄されている現状からも、こうした取り組みは積極的に続けていかなければと思っています」。
患者さんの様子や状態を的確に見極め、その時々でコミュニケーションを深めたり、配達だけにとどめたりする、桃原さんの人柄そのものを映し出すような温かみあるサービスです。重要なのは「在宅訪問」という言葉ではなく、患者さんへ寄り添うことなのでしょう。

薬剤師不足の沖縄で積極的にシニア世代を採用
慢性的な薬剤師不足が続く沖縄。薬剤師会の理事会をはじめ、医療関係者が集まる様々な会合の場では、「顔を合わせると『薬剤師、いない?』が合言葉になっている」(桃原さん)というほど、人手不足は深刻な状況だと言います。
ふてんま薬局も例外ではない中、桃原さんはシニア世代の薬剤師の採用に乗り出しています。現在、70代薬剤師は4~5名。薬剤師としてのスキルはもちろん、人生経験にも期待していると話します。それぞれ、福岡や広島など沖縄以外のエリアから応募し、採用を機に沖縄に移住された方ばかりです。
「薬剤師にとって服薬指導はもちろん必須ですが、そのために重要となるのはその患者さんの生活環境や職業など、バックグラウンドを理解しようとする努力。服装や雰囲気、話している内容から、『夜勤が多い仕事かな』とか、『朝晩は薬が飲めるけど昼は飲めない環境かな』とか、そういうことをさりげなく感じ取ったり、引き出したりできるのは、やはり経験を積んだ薬剤師の方が上手です。若い薬剤師は、彼らのようなコミュニケーションスキルをどんどん学んでほしいと思います」と、桃原さん。
しかしながら、沖縄には現在も薬学部がなく、地元で生まれ育った若者は県外で学ぶしか道がありません。こうした状況を変えるべく、厚生労働省が発出した「薬剤師確保計画ガイドライン」を踏まえ、沖縄では「沖縄県 薬剤師確保計画」を策定し、県内での就職あっせんや薬学部設置などの議論が高まり、大きな注目を浴びています。
これからの薬剤師が目指す姿
「2040年、2050年と、ますます高齢化が進む中、薬剤師は大きな変化を求められています。薬局でじっと処方箋を待つのではなく、『行動する薬剤師』を目指していかなければなりません。患者さんをもっと身近に感じるため行動する必要があります。また多職種と一つのチームになり、薬剤師としての能力を発揮するシーンも出てくるはずです。治療は医師に任せるけれど、薬のことは専門家である薬剤師に任せよう、という体制を整えるべきです。時間はかかりますが、薬剤師がチームの中で能力を発揮できるようになれば、医療にとっても大きな力になるはずです」と桃原さん。
加速度的に変化していく時代において、桃原さんの温かみのある人柄やどこまでも患者さんに寄り添うスタイルは、決して失われてはいけない貴重なものでしょう。
編集:株式会社 医学アカデミー



