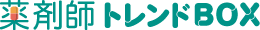TOPICS
時代とともに変わる薬局
~大阪万博を機にこれまでをたどる~
薬剤師トレンドBOX#49
2025年春から、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪・関西万博が開催されます。大阪で万博が開催されるのは、1970年(昭和45年)以来、実に55年ぶりです。
前回の大阪万博では、当時最先端の技術が披露されましたが、この55年の間、医療や薬学の分野でも大きな発展が見られました。特に、「薬局」や「薬剤師」に期待される役割は大きく変化してきました。今回は、近代の薬局や薬剤師の歴史を振り返ります。

「薬局」や「薬剤師」の礎が築かれたのは約150年前
薬の歴史は古く、日本では古事記にも薬について記載されています。特に江戸時代に入ると、薬の流通や販売が活発になり、「売薬」という形で一般庶民にも広まりました。また、家庭や職場に薬箱を設置し、使用した分の薬の料金を回収する仕組みである「置き薬」が生まれましたが、「薬局」や「薬剤師」といった言葉はまだ使われていませんでした。
明治時代になると、海外の制度を参考にしながら、ようやく日本でも医薬分業が始まります。1874年(明治7年)にはドイツの制度を参考に、日本で最初の医療法規である医制が制定され、医薬分業の原則が初めて法律で規定されました。薬の販売を行う場所が「薬舗」と位置付けられ、薬舗主に調剤権が与えられたことで、薬局や薬剤師の礎となる体制が確立され始めます。
その後、1889年(明治22年)には薬品営業並薬品取扱規則(薬律)が制定され、「薬局」や「薬剤師」という名称が正式に定められ、現在の医療に近づく大きな一歩を踏み出しました。
第二次世界大戦で医療体制は悲惨なものに
海外に習い、進歩し始めた日本の医療ですが、1939年(昭和14年)から始まった第二次世界大戦により、医療施設や医療体制も大きな影響を受けることになります。戦災で多くの医療施設が破壊・閉鎖され、医療従事者の不足や食糧・医薬品・衛生材料の不足と相まって、日本の医療状況は悲惨なものとなりました。
壊滅した医療体制の立て直しのため、終戦後の1945年(昭和20年)には占領軍から旧日本軍の陸海軍病院等が返還され、1948年(昭和23年)には医療法、医師法が定められました。戦災で大きなダメージを受けた医療機関や医療体制が徐々に整備され始めます。
しかし、医薬分業に関しては、1956年(昭和31年)には医薬分業法、1960年(昭和35年)には薬事法や薬剤師法が定められたにも関わらず、依然として院外処方は広まりませんでした。
1970年代から、医薬分業に大きな変化が
前回の大阪万博が開催された1970年は、医薬分業がなかなか広まらなかった頃だったといわれています。現在7割を超える処方箋受取率ですが、この頃は1%にも至っていませんでした。この状況を一変させたのが、1974年(昭和49年)の診療報酬改定です。処方箋料を10点から50点へ引き上げたことで、院外処方箋の発行枚数も大幅に増え、医薬分業が加速しました。このことから、1974年は医薬分業元年ともよばれています。
徐々に医薬分業が進み、薬局や薬剤師に求められる役割が増えていくなかで、1990年代にはその質的向上が話題に上がるようになります。
1992年(平成4年)には医療法が改正され、薬剤師は医療の担い手として明記されました。2000年代に入ると、薬学教育が6年制に変更され、在宅医療や医療安全などへの関わりも薬剤師に期待されるようになりました。
時代にあわせて変わっていく「薬局」や「薬剤師」
薬と薬剤師の役割は時代とともに大きく変化してきました。江戸時代には売薬や置き薬が主流でしたが、薬局が徐々に発展し、戦後には調剤薬局という新しい形態が誕生しました。そして、現代では医薬分業の進展や在宅医療の普及により、薬剤師の役割はより広範になっています。
薬剤師は長らく、調剤を中心に患者の服薬を支える役割を担ってきました。現代では、対物業務に加え、対人業務の強化が求められ、具体的には、かかりつけ薬剤師・薬局としての継続的な服薬指導や在宅医療への対応、夜間・休日の対応、健康サポートやセルフメディケーション支援など、幅広くさまざまな役割が期待されています。また、医療機関や介護施設との連携を強化し、地域医療の一翼を担う役割も重要視されているほか、今後は医療DXの推進による情報共有やICTの活用を通じ、より効果的な薬学的管理への進化も求められています。日々変わっていく社会情勢の中で、柔軟に変化し続ける薬局・薬剤師が必要とされているのかもしれません。

(2025年4月掲載)
編集:株式会社 医学アカデミー