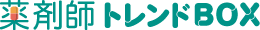TOPICS
疲れをリセット!
質のよい睡眠のために
薬剤師トレンドBOX#48
暦の上では春になりましたが、まだまだ冷える日の続く季節。寒くて眠りが浅くなってしまったり、布団から出られなかったりする人も多いのではないでしょうか。睡眠健康推進機構はWorld Sleep Dayにあわせて、3月18日を「睡眠の日」と定めています。今回は、薬剤師なら知っておきたい睡眠の知識と、よい睡眠のためのポイントを改めて確認していきましょう。

現代の日本人は約4割が睡眠不足
睡眠は、こどもから高齢者まですべての年代において、健康を保つために欠かせない重要な休息の手段。睡眠不足は日中の眠気や疲労を招くだけでなく、慢性的な睡眠不足や睡眠の質の低下により、様々な疾患の発症や再燃・再発に影響することが知られています。
成人では1日あたり6~8時間の睡眠時間が望ましいといわれていますが、令和5年の国民健康・栄養調査結果において、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は、男性では38.5%、女性では43.6%であり、性・年齢階級別にみると、30~50歳代の男性、40~60 歳代の女性では4割を超えていることが示され、日本人は十分な睡眠時間が確保できていないことがわかります。
また、睡眠時間をただ確保するだけでなく、睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)も大切であることが知られています。しかし、調査によると、睡眠で休養がとれている人の割合は年々減少傾向にあることがわかっています。不眠症状を有する人も多く、睡眠時間の短縮に加え、睡眠の質も低下しているといえるでしょう。
厚生労働省では「適正な睡眠時間の確保」と「睡眠休養感の向上」を重要課題と位置づけ、日本の健康寿命の延伸のために、「健康づくりのための睡眠ガイド」を作成し、取り組みを進めています。
不眠の症状とその原因
不眠症状には、寝つきの悪い「入眠障害」、眠りが浅く途中で何度も目が覚める「中途覚醒」、早朝に目が覚めて二度寝ができない「早朝覚醒」などのタイプがあります。
一般成人の30〜40%が何らかの不眠症状を有しており、女性に多いことが知られています。不眠症状のある方のうち、慢性不眠症は成人の約10%に見られ、その原因はストレス、精神疾患、神経疾患、アルコール、薬剤の副作用など多岐にわたります。 1)
不眠の原因
● ストレス
ストレスと緊張はやすらかな眠りを妨げます。神経質で生真面目な性格の人はストレスをより強く感じ、不眠にこだわりやすく、不眠症になりやすいようです。
● からだの病気
高血圧や心臓病(胸苦しさ)・呼吸器疾患(咳・発作)・腎臓病・前立腺肥大(頻尿)・糖尿病・関節リウマチ(痛み)・アレルギー疾患(かゆみ)・脳出血や脳梗塞など様々なからだの病気で不眠が生じます。不眠そのものより、背後にある病気の治療が先決です。原因となっている症状がとれれば、不眠はおのずと消失します。
● こころの病気
多くのこころの病気は不眠を伴います。近年は、うつ病にかかる人が増えています。単なる不眠だと思っていたら実はうつ病だったというケースも少なくありません。不眠症状や過眠症状(眠気)とともに、気分の落ち込みや意欲減退(何事も億劫)、興味の減退(趣味が手につかない)などの症状がみられる場合には早めに専門医を受診してください。
● その他の睡眠障害
睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)など、睡眠に伴って呼吸異常や四肢の異常運動が出現するために睡眠が妨げられ、不眠症状が出現する場合も珍しくありません。
● 薬や刺激物
治療薬が不眠をもたらすこともあります。睡眠を妨げる薬としては、降圧剤・甲状腺製剤・抗がん剤などが挙げられます。また、抗ヒスタミン薬では日中の眠気が出ます。コーヒー・紅茶などに含まれるカフェイン、たばこに含まれるニコチンなどには覚醒作用があり、安眠を妨げます。カフェインには利尿作用もあり、トイレ覚醒も増えます。
● 生活リズムの乱れ
交替制勤務や時差などによって体内リズムが乱れると不眠を招きます。現代は24時間社会といわれるほどで昼と夜の区別がなくなってきていますから、どうしても睡眠リズムが狂いがちです。
● 環境
騒音や光が気になって眠れないケースもみられます。また寝室の温度や湿度が適切でないと安眠できません。
e-ヘルスネット 不眠症|厚生労働省
1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努め、睡眠環境や生活習慣、嗜好品の摂り方などを見直して改善することにより、睡眠の質を高める必要があります。
睡眠の質の向上のためのポイント
睡眠に対して悩む患者さんと出会ったときには、まずは患者さんの生活環境や一日の過ごし方を確認し、問題点が見つかった場合には改善できるようなサポートや声かけを行うことが大切です。
環境を整える
- ・日中にできるだけ日光を浴びる
- ・寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まず、できるだけ暗くして寝る
- ・寝室は暑すぎず寒すぎない温度に調整する
- ・就寝の約1~2時間前に入浴しからだを温める
- ・できるだけ静かな環境で、リラックスできる寝衣・寝具で眠る
運動、食事等の生活習慣を整える
- ・適度な運動習慣を身につける
- ・しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控える
- ・眠気が訪れてから寝床に入る
- ・日中の活動と夜間の睡眠のメリハリをつける
気温が低く、日照時間の短い冬は、外出の機会が減少する患者さんも多いでしょう。室内の環境を整えるのはもちろんのこと、適度な外出や運動習慣が質のよい睡眠の助けとなります。外出が難しい場合には、室内で歩き回ったり、家事を行ったりと、無理のない範囲で活動量を上げられるようアドバイスできるとよいでしょう。
特に高齢者においては、長い床上時間が健康リスクを高めると考えられています。また、眠れないときに無理に眠ろうとすると余計に眠れなくなってしまいます。温かいからといって布団の中で長く過ごすのではなく、入浴をしてからだを温め、眠気が訪れてから寝床に入るのも有効です。
なお、嗜好品については、カフェインの摂りすぎや夕方以降のカフェインの摂取、深酒や寝酒(眠るためにお酒を飲むこと)、喫煙などは睡眠の質を下げるといわれています。可能な限り摂取しないようにするか、量を減らせるような支援が必要です。
また、休日にまとめて睡眠時間を確保する「寝だめ」では睡眠時間をためられないことがわかっています。夜間の良眠のためにも、休日の寝だめや長時間の昼寝は避け、規則正しい生活を送ることが大切です。
環境や生活習慣を整えても、「十分な時間眠れない」、「睡眠で休養感が得られない」、「日中の眠気が強い」などの症状が継続し、それらの症状が日中の生活に影響を及ぼしているときは、不眠症などの「睡眠障害」の可能性があり、医師の診察や治療が必要になる場合があります。患者さんの生活を細かく聴取しつつ、必要に応じて受診を勧めることも検討しましょう。
患者さんの一日の過ごし方を確認
冬は日照時間の短さや寒さなどにより活動量が低下したり、こたつで居眠りをしてしまったりと、睡眠の質が低下してしまう患者さんも多いはずです。「よく眠れない」と患者さんからお話があったときには、実際の睡眠時間や症状はもちろん、一日の過ごし方や寝室の環境なども確認できるとよいですね。

(2025年2月掲載)
編集:株式会社 医学アカデミー