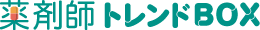TOPICS
それって本当にカロリーゼロ!?
~服薬指導に添えたい低カロリー加工食品の知識~
薬剤師トレンドBOX#47
バレンタインが近づき、甘いものの誘惑だらけの時期がやってきました。そんなときに惹かれてしまうのが、「カロリーゼロ」や「カロリーひかえめ」と謳われる低カロリー加工食品。積極的に利用している患者さんも多いかもしれません。ドラッグストアなどでも数多く販売されていますが、安心して勧めてよいのか疑問に思ったことはありませんか。今回は、服薬指導に添えたい低カロリー加工食品の知識とポイントを解説します。

食品の表示ルールを定める食品表示法
カロリーとは、熱量(エネルギー摂取量)を示す単位のことで、エネルギーは生命機能の維持や身体活動に利用されます。熱量は、2015年に施行された食品表示法により、たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムとあわせて、容器包装に入れられた加工食品への表示が義務化されています。
食品表示法の施行以前には食品の表示についてルールを定める法律として、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止するための「食品衛生法」、農林物資の品質の改善と、品質に関する適正な表示により消費者の選択を手助けするための「JAS法」、栄養の改善やその他の国民の健康の増進を図る「健康増進法」の3つがありました。しかし、それぞれに表示のルールが定められており、複雑でわかりにくいものになっていたことから、規定を統合する食品表示法が施行され、食品表示基準に具体的な表示のルールが規定されました。
食品表示法(平成25年法律第70号)
【目的】
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保
【食品表示基準のポイント】
① 加工食品と生鮮食品の区分の統一
② 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③ アレルギー表示に係るルールの改善
④ 栄養成分表示の義務化
⑤ 新たな機能性表示制度の創設
※「食品表示法」及び食品表示法に基づく「食品表示基準」は平成27年4月より施行。
低カロリー加工食品と食品表示基準
「カロリーゼロ」というと、カロリーがまったく含まれていないと解釈してしまいがちですが、実際にはそうではありません。食品表示法とそれに基づく食品表示基準において、100g当たり5kcal未満の食品や100ml当たり5kcal未満の飲料は「カロリーゼロ」や「ノンカロリー」などと表示してよいとされています。「○○ゼロ」や「○○豊富」、「○○ひかえめ」など、栄養成分を多く含む場合や含まない場合、糖類やナトリウム塩を添加していない場合に使用できる表示は、栄養強調表示といいます。
| 栄養強調表示の種類 | 含まない旨 | 低い旨 | 低減された旨 |
|---|---|---|---|
| 表現例 | カロリーゼロ、 ノンカロリー等 |
低カロリー、 カロリーひかえめ等 |
カロリー○%カット、 カロリー○%減等 |
| 基準 | 食品100g(100ml)当たり5kcal未満 | 食品100g当たり40kcal(100ml当たり20kcal)以下 | 他の同種の食品に比べて食品100g当たり40kcal(100ml当たり20kcal)以上の低減、かつ、25%以上の相対差 |
これらの栄養強調表示は、100gまたは100ml当たりで基準が決められており、「カロリーゼロ」と表示されていたとしても、1日に大量に摂取した場合には、結果的にカロリーが増えてしまうため、注意が必要です。
カロリーを抑えられる理由と健康へのリスク
低カロリー加工食品には、砂糖の代わりに甘味料を利用することで美味しさを維持しつつ、カロリーを抑えているものが多くあります。
国内で使用されている甘味料は、食品添加物として内閣府の食品安全委員会による安全性の評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限り、成分の規格や使用の基準を定めて使用が認められています。
一方、これらの甘味料の使用については、現在も世界各国で議論がなされています。WHOは、2023年に公表したガイドラインの中で、非糖類甘味料(non-sugar sweeteners、NSS)を体重管理のために使用しないよう勧告しました。
日本でも使用されている非糖質甘味料の例
・アセスルファムK(acesulfame K)
・アスパルテーム(aspartame)
・アドバンテーム(advantame)
・ネオテーム(neotame)
・サッカリン(saccharin)
・スクラロース(sucralose)
・ステビア(stevia)及びステビア誘導体(stevia derivatives) 等
これらの甘味料の使用が成人又は小児における体脂肪減少に長期的な利益をもたらさないことが示唆され、長期使用による2型糖尿病や心血管疾患、及び成人の死亡率のリスクとの関連にも触れています。
ダイエットや食事制限をしている人にとっては、とても魅力的に見える低カロリー加工食品ですが、大量の摂取や体重管理のための長期的な使用などについては、慎重に判断することが求められています。
服薬指導のポイント
食事の制限がある患者さんをはじめ、自分や家族の健康のために積極的に低カロリー加工食品を選んでいる患者さんも多いと推測されます。反対に、甘味料などの食品添加物を不安に思っている患者さんもいるかもしれません。
薬剤師として、患者さんやその家族の気持ちを理解しつつ、エビデンスに基づいたアドバイスができるとよいでしょう。また、甘味料や食品添加物に対する考え方については、医療従事者の中でも意見が分かれることがあります。特に食事制限が必要な患者さんの場合には、主治医からどんな説明を受けているか、確認できるとよいでしょう。
健康のためには、バランスのよい食事や適度な運動が大切です。低カロリー加工食品を上手に利用しながら、自分らしく生き生きと生活できる手助けができるとよいですね。

(2025年1月掲載)
編集:株式会社 医学アカデミー