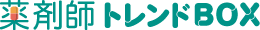TOPICS
異常気象で服薬指導のあり方が変わる!?
“気象薬学”という新たな社会薬学的アプローチ
薬剤師トレンドBOX#10
2016年は昨年末からの暖冬を受けて各地で梅や桜の開花が各地で記録的な前倒しとなるなど、季節感のズレに戸惑わされる状況が顕著です。このまま猛暑を迎える見通しから引き続き熱中症が警戒されていますが、こうした異常気象や気候の変動を社会薬学的に応用する試みが進みつつあります。
「ここ10年ほどで高齢者を中心に熱中症が急増したわけですが、その背景には異常気象とともに医薬品の作用機序もあげられ、実際に医薬品医療機器総合機構(PMDA)には降圧剤や糖尿病薬といった薬剤の有害事象に『熱中症』が加えられています」。
そう解説するのは、千葉県市原市で40年以上薬局を営むキャリアと実感に基づき、数年前から県薬剤師会の社会薬学委員会を通じて天候・気象を踏まえた薬剤師業務の検討に取組む伊藤均氏。2015年の第48回日本薬剤師会学術大会に際しては、PMDAに寄せられる熱中症に関わる薬剤の有害事象報告と救急外来の疾病統計、気象庁が取りまとめる天気図・気象要素データなどとの関連性を調べる試みを通じ、適切な服薬指導と薬歴管理を図る手法としての“気象薬学”を提唱する論文をポスター発表しました。
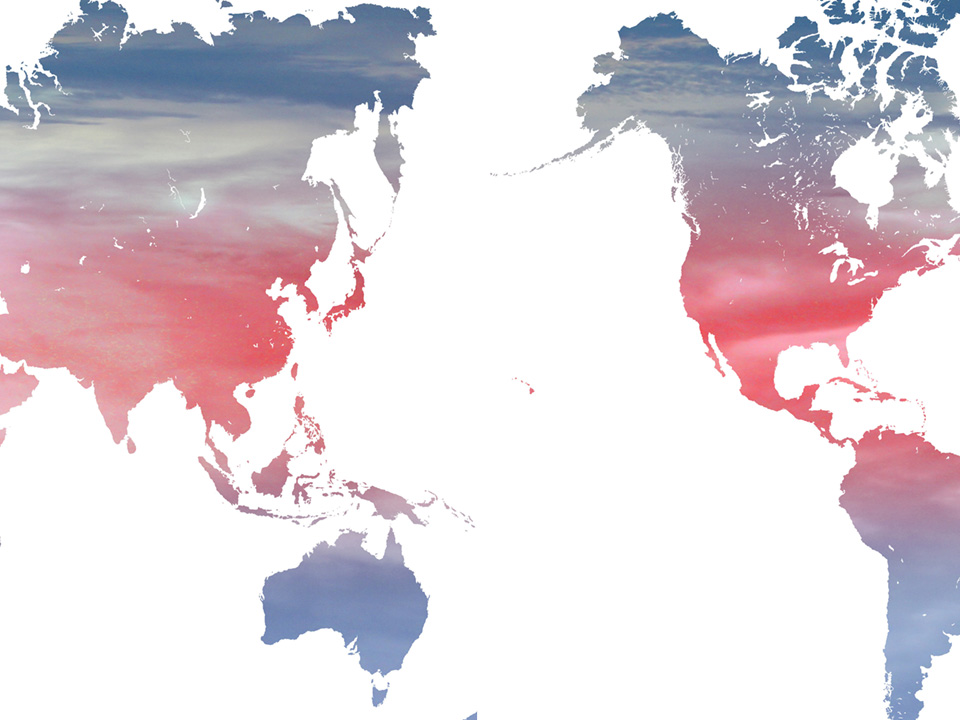
頭痛や神経痛、盲腸(虫垂炎)における天候との因果関係をはじめ、気象状況が身体や体調、疾病に影響を与えることは昔から保健・医療で考慮されています。熱中症問題を象徴に、近年の異常気象の発生頻度に比例して影響力が強まっているのは容易に想像されるところで、さらに高齢社会の進展といった要素も加わるなかで薬物療法においても何らかの対応を考える必要性が増していると言えます。
そもそも気象薬学を思い立ったきっかけとして伊藤氏は、高齢化と長期処方の定着をあげています。「高齢化で増えている病名を薬剤師として注意深くみていくと、実は副作用や他の要因なのではないかと考えられる状況は少なくありません。さらに処方の長期化では、仮に診察時の気象の影響を受けた症状に対して薬が追加されていたとすれば過剰投与になってしまいます」。
処方時に投薬された薬が果たして1か月後にも適切かどうかを見極めることは、言うまでもなく調剤における昨今の薬剤師業務に重要性を増す姿勢と技術。その視点を養うための1つの要素として、伊藤氏は気象を考慮した対応を強調しています。

また、伊藤氏はPMDAで熱中症の有害事象が報告される医薬品が処方された場合、その時の気象状況を勘案しながら投薬段階で熱中症に対する注意を促すとともに、正しい水分摂取を指導するといったセルフメディケーションの働きかけに結び付ける機会にも活用していると言います。
「専門的な観点で昨今の異常気象に対する注意を呼びかけることも、地域の健康情報拠点に期待される薬局・薬剤師の役割になるのではないでしょうか。天候といった身近な生活で関心を引く情報を取り入れることにより、服薬指導の内容に対する理解を深めながら、患者にセルフメディケーションの意識を高める効果も期待できると感じています」。
こうした可能性を感じさせる手応えは、まさにベテラン開局薬剤師ならでは。気象薬学のようなアプローチが今後、かかりつけ薬剤師のスキルとして確立・発展していく可能性が注目されます。

(2016年7月掲載)
編集:薬局新聞社